養蚕地域の繁栄と大不況 |
|
| 明治維新後、西欧と肩を並べようとする日本は、外貨を獲得するために生糸の輸出に力を入れた。そのため、生糸の価格が上がり、現金収入の少なかった養蚕地域の農家は、貨幣経済に巻き込まれていった。 輸出生糸好況の中で、農民たちの暮らしぶりは様変わりし、秩父の養蚕農家でもうまいものを食べ、女は化粧をしたり髪飾りをつけておしゃれもするようになった。 貿易港である横浜から、更にはフランスはリヨンの生糸相場に目を向けるようになった農民たちは、明治政府の殖産興業の名の下に、養蚕、製糸の改良に取り組み、小生産者として自立をしていった。 また、生糸相場の情報とともに入ってくる、フランスの民権思想は、一部インテリの人たちに受け入れられ、それらの人々は、自由党の活動にも呼応して、現憲法の思想にも通ずる、開けた考えを持つようになっていった。 |
|
1881年 (M14) |
松方正義、大蔵卿就任 明治10年の西南戦争以来不換紙幣を乱発したために続いていたインフレを収めるために、松方大蔵卿は大増税と紙幣整理を強行した。そのために起きたデフレのために物価と賃金は暴落し、不況の波は秩父の養蚕農家にも襲いかかった。 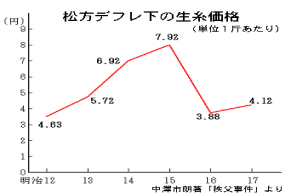 生糸暴落と増税に苦しむ農民は、相場の好転を期待して高利貸しから資金を借り受けた。 |
| 1883年 (M16) |
生糸相場はいっこうに好転せず、農民の暮らしはますます苦しくなった。10円の借入金が、
1年後には 3倍近くにもなるという違法な高利の罠にはまってしまった農民は、次々と土地や家を奪われることになる。 12月、上吉田村・高岸善吉、下吉田村・坂本宗作、落合寅市が、秩父郡役所に違法な高利貸し説諭方の請願をするが、却下される。 |
| 1884年 (M17) |
自由党との接触、合法活動から蜂起へ |
| 2月、自由党員大井憲太郎、秩父遊説 3月、自由党春季大会に、秩父から高岸善吉ら 5名参加。 8月、小鹿野町近隣の山で、困民党第1回山林集会。高岸善吉、落合寅市、井上善作、飯塚森蔵ら13名が参加し、負債問題について話し合う。 8月、第2回山林集会。27名が参加し、高利貸しへ直接交渉をするが、警官隊に逮捕される。その後、あちこちで山林集会が開かれる。 9月6日、田代栄助、阿熊村新井駒吉宅で、高岸善吉、坂本宗作、井上伝蔵、小柏常次郎らと合い、協力を要請される。「諸君何レモ一命ヲ棄テ万民ヲ救フノ精神ナレハ速ニ尽力セシ」(訊問調書)と答える。 9月、高岸善吉、犬木寿作、飯塚森蔵、村竹茂一らを先頭に、負債農民の連名委任状を持って大宮郷(現秩父市)警察署に対して違法な高利貸しについて請願運動を始める。だが、連名では不都合と受理されない。 10月、高利貸しとの集団交渉。 裁判所と癒着した高利貸しは態度を強め、取り立てがいっそう厳しくなる。委任状を出した農民に対して、借金を返せない故に裁判所から召喚状が出される。 追いつめられた困民党は、蜂起に向けてオルグ活動をいっそう強める。 自由党員を中心としたオルグは、秩父のみならず、山を越えた寄居方面から上州、信州までに及ぶ。 風布村の大野苗吉は「オオソレ乍ラ、天朝様ニ敵対スルカラ加勢セヨ」と村の農民に呼びかけた。 10月12日、下吉田村井上伝蔵宅に、田代栄助、伝蔵、高岸善吉、坂本宗作、小柏常次郎、落合寅市、井上善作、新井周三郎、門平惣平らが集まる。善吉と伝蔵は栄助に蜂起への同意を求める。 10月26日、下吉田村粟野山で会議。蜂起の期日を話し合う。 他県での一斉蜂起準備のため1ヶ月延期を主張する栄助に対し、小柏常次郎や一刻も猶予のない負債農民は、28日蜂起を主張。結局、栄助が妥協して、11月1日蜂起と決定する。 10月29日、自由党解党 困民党の農民たちが「金のないのも苦にしやさんすな 今にお金が自由党」と歌い、期待をしていた自由党は、党内左右の分裂から解党してしまった。農民たちはそのことを知らず、「板垣の世直し」と唱えながら蜂起の参加者を増やしていった。 10月31日、困民党本部よりいち早く、風布村の農民は村内の金比羅神社に集結し、蜂起した。新井周三郎を中心とした日野沢村農民は金崎村の金貸し会社、永保社を襲撃して証書類を焼き払い、警官隊と小競り合いをしながら下吉田村の椋神社に向かった。 それまで内偵を続けても農民の動きを掴めなかった寄居警察署は、このときになって初めて「秩父郡風布村金尾村ノ困民等飛道具ヲ携ヘ小鹿野地方ヘ暴発スルノ景況ナリ」と県警本署に電報を送った。 |
|
困民党蜂起、大宮郷占拠 |
|
| 11月1日、夕刻、下吉田村椋神社に困民党農民が続々と集結し始める。約三千に達した農民たちの前で、田代栄助が役割表を、菊池貫平が軍律を読み上げた。 午後8時、甲乙2隊に分かれた困民軍は、小鹿野に向けて進軍を始める。高利貸しの家を襲撃しながら小鹿野町に到着した困民軍は、警察分署、戸長役場、高利貸しの家を襲撃し、小鹿野諏訪神社を本部とした。 |
|
| 11月2日、早朝に出発した困民軍は、鉄砲隊、竹槍隊、抜刀隊と続いて大宮郷を目指した。 大宮郷の役所、警察署は、前夜に知らせを受けてもぬけの殻となっていた。見つかるのを恐れ、髭を剃って逃げた警官もいたという。困民軍は市内を見下ろせる札所23番音楽寺の鐘を打ちならし、大宮郷へとなだれ込んだ。 いったんは秩父神社に本部を置こうとした困民軍だが、菊池貫平の進言で、郡役所に革命本部を置いた。 「今日ヨリ郡中ノ正則ヲ出ス事大将ノ権ニアリ。各其意ヲ体セ」 大宮郷を支配下においた困民軍は、市内の悪徳高利貸しの家を襲ったり、周辺地域へかり出しにでたり、また市内で軍事訓練を行ったりと忙しい一日を過ごした。また、豪家から軍用金調達が行われ、その領収書には、総理田代栄助の名の他、「革命本部」の文字も見られる。そこに、困民軍が暴動ではなく、民権思想に基づいた革命を起こそうとしていた心うちが読みとれる。 市内にある矢尾商店(現、矢尾デパート)には、日記「秩父暴動事件概略」が残されている。 「十一時ヲ期シ暴徒等大宮郷ヘ繰リ込ム由・・・・疾クモ兇徒等潮ノ涌クガ如ク市中ヘ乱入シ一整ニ鯨声(とき)ヲ揚ゲ、疾風ノ如ク市中ヲ通過シ、先駆ハ忽チ警察署ノ辺ヨリ猟銃ヲ以テ連発シ、裁判所、警察署ニ狙撃乱入シ両役所ノ書類ヲ引裂キ或ハ戸外ヘ投棄シ或ハ火ヲ焚キ之ニ投ジ・・・・手当リ次第ニ打砕キテ書類ノ紙片ハ市中ニ散乱シテ、時ナラザルニ雪ヲ降ラシタリ」(秩父暴動事件概略) また、会計兼大宮郷小隊長柴岡熊吉が来店し、「此度世直ヲナシ、政治ヲ改革スルニツキ、斯ク多数ノ人民ヲしゅう集セシ訳ナレバ、当店ニテ兵食ノ炊出シ方ヲ万端宜シク頼ム。扨(さ)テ高利貸営業者ノ如キ不正ノ行ヲナス者ノ家ニアラザレバ破却或ハ焼棄ナスナド決シテ致サズ。又々高利貸ノ家ヲ焼キタリトモ、其隣家ニ対シ聊(いささ)カモ損害ヲ加エヌ故、各々安堵致サレタシ。且ツ不法ヲ云ヒ或ハ乱暴ヲナス者コレアラバ直ニ役所ヘ届ケ出ツベシ。夫々成敗ヲ致スベキ間左様心得ラレタシ。右ノ次第ナレバ当御店ニテハ安心シテ平日ノ如ク見世ヲ張リ商業ヲ充分ニナサレタシ」と述べている。 しかし、夜になっても困民軍は鯨声をあげたり、鉄砲の訓練をしたりと、市内は騒然とし、人々は不安な夜を迎えることとなった。 埼玉県書記官笹田黙介は、この日午前11時に内務大臣山県有朋宛に電報を打っている。 「県下秩父郡ノ暴徒既ニ千人ニ及ビ、抜刀銃器ヲ携ヘ、同郡小鹿野町ニ火ヲ放チ、大宮郷ニ向ケ押出ス模様アリ・・・・都下ニ近接セルニ依リ、若シ影響スルコトアリテハ容易ナラザルニ付早ク鎮定シタシ。至急憲兵ヲ御派遣アレ」 また、午後9時、笹田書記官は次のような電報を受ける。 「憲兵一小隊春日少佐是ヲ率ヒ同夜十一時発本庄駅マデ別仕立汽車ニテ派遣ス」 秩父方面に、憲兵三個小隊、鎮台兵一個大隊が派遣されることとなった。 |
|
| 11月3日、権力側が動き出した情報は誤報に誤報を重ね、困民軍は振り回され始める。多地方での一揆勃発との誤報も入り、困民軍は大宮郷の守りもそこそこに、軍を甲乙丙3隊に分け、各方面に動き始めてしまった。 熊谷で一揆が起こったとの誤報を信じて、愛宕神社で大宮郷北の守りをしていた乙隊菊池貫平は、皆野へと進出してしまう。荒川の河原で憲兵隊と遭遇し、撃ち合いとなる。憲兵隊は装備の銃と弾丸が違っていて撃つことができず、火縄銃を持った農民に敗退させられる。 |
|
信州への遠征・困民党解体へ |
|
| 11月4日、皆野対岸の大淵村に布陣していた甲隊に捕虜となっていた青木巡査は、隙を見て甲大隊長新井周三郎に斬りつけて重傷を負わせて戦死する。 革命本部を守るはずの丙隊も、田代栄助らと共に皆野に進出していた。運び込まれた新井周三郎を見て、農民たちはパニック状態となり、軍列を乱し始める。その様子を見た田代栄助、井上伝蔵、犬木寿作らは、蜂起ももはやこれまでと察して山中へ姿を消し、本陣は解体する。 困民軍の姿が消えた大宮郷では自衛組織が結成され、その動きは各地に広がり始める。 本陣解体を知らずに各地へ転戦している困民軍は、東京から派遣された鎮台兵とあちこちでぶつかり、惨劇の後にちりぢりとなっていく。 知らぬうちに本陣が解体したことを知った菊池貫平は、新たに総理となり、困民軍を組織し直すと、信州へ向けて進軍を開始する。 |
|
| 11月9日、十石峠を越えて信州佐久へと進出した困民軍は、千曲川流域の東馬流で、待ちかまえていた高崎鎮台兵に急襲される。さらに野辺山まで逃れた困民軍は、鎮台兵の新式銃にかなわず、ちりぢりとなってしまう。 ここに、9日間にわたって展開された困民党の蜂起は終わりを告げる。 |
|
| 困民党解体後、秩父一帯は残兵狩りと捜査に入った官憲に蹂躙され、農民たちは新たな恐怖の日々を送ることとなる。また、課せられた罰金により、更なる困窮生活を強いられることとなった。 |
|
| 困民党蜂起は「火付け強盗」あるいは「博徒」の暴動とされ、逮捕者は国事犯扱いされずに刑事罰を与えられることとなった。 また、長く秩父では朝廷に背いた暴徒ということで、この事件を恥じ、口をつぐんできた。近年になり、ようようこの事件が先駆的な思想に基づき、困民を救うために起こされたということが広く知られるようになった。 |
|