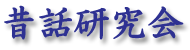 「無文字時代の動物寓話」 〜「稲葉の素兎」誕生まで〜
「無文字時代の動物寓話」 〜「稲葉の素兎」誕生まで〜
民間説話の通時的研究
−その方法論覚え書き−
1999.9
稲 田 浩 二
参考論文
1 「『稲葉の素兎』試論 −その通時的国際性」
「梅花児童文学」4(1996)
<『昔話の源流』(1998三弥井書店)収載>
2 「チ・ランケ・ハル −日本農耕文化の二つの底流」
「梅花児童文学」7(1999)
3 「縄文人のメッセージ」(エッセイ)
「ちくま」(1999.9.1)
1 無文字時代文化の研究
1) 考古学・人類学の対象−遺物・遺跡・人骨など
2) 美術研究の対象−絵画・彫刻など
3) 文芸研究の対象−口承文芸(民間説話・民謡など)
2 民間説話研究のプロセス<1>
1) 研究対象のモチーフ構成分析
モチーフ構成は可変的
2) 核心モチーフの認定 例−その持続性
1 「蛇婿入り−針糸型」(IT205A)の「男に変身した蛇が女と結婚する」−記紀
2 「蛇婿入り−嫁入り型」(IT205D)の「人が異類に水に浮かべたひょうたんを
沈ませて、その神性をただす」−「仁徳紀」
3 参考−洞窟絵画の主題としての馬
ルロア・グーラン・アンドレ 1964 改訂第三版、蔵持不三也訳
『先史時代の宗教と芸術』1985 日本エディタースクール出版部
横山祐之『芸術の起源を探る』 1992 朝日出版社
3) 核心モチーフの生まれた時代・民族・地域
3 研究のプロセス<2>
1) その核心モチーフをもつ口承の民間説話資料
1 国際的に、近くより遠きへ
2 無文字民族の資料を重視
2) その民間説話をめぐる儀礼・民俗などに留意
4 研究のプロセス<3>
1) その核心モチーフをもつ古典(国書・外書)資料
2) その古典の成立年代は、その核心モチーフの生まれた時代の下限
3) 口承資料と文献資料の異同に留意
5 研究のプロセス<4>
1) 隣接諸科学の援用
考古学 人類学 文化人類学 民族学 民俗学 他
6 「『稲葉の素兎』試論」再考
1) 『古事記』「稲葉の素兎」
1 A.D.8C 建国英雄神話の冒頭部分
2 モチーフ構成
1. 兎がワニにお互いの仲間の数くらべをしようと提案すると、ワニは岸から
対岸まで浮かび並ぶ。
2. 兎がその上を渡りながらかぞえ、欺いたことを
口走ると、ワニは怒って兎の皮をはぐ。
2) 「稲葉の素兎」の口承類話
1 シベリア東北部、サハリン
2 東南アジア
3) A.D.1C 以前 『三国志』魏書、東夷伝「夫餘」他、建国英雄神話
「魚鼈浮為橋」 −神話モチーフ(神話的修辞的表現)
7 「魚鼈の橋」から「稲葉の素兎」まで −動物寓話の起源の一例
1 矚目の情景 → 「魚族の橋」ツーク−修辞的表現 → 神話モチーフ
「草木もの言う」時代(紀)、聖なる動物は畏怖の対象。その霊力で建国英雄を
援助する。記紀の八咫鳥も。トーテム時代。
2 異類の神の零落
異類の神が人間の営み(農耕)を妨げ、その生命をおびやかすとき、英雄がそ
れを退け、古い神として祭る。(『常陸風土記』、「仁徳紀」など)
3 異類は人間と同次元のものとされ、彼らの特徴によって人間の代役をつとめ、
民間の語り部により動物寓話の登場者となる。−動物寓話のモチーフ成立。
<環日本海の諸民族で>
4 シャーマンの巫術
死に瀕した登場者(ウサギ・キツネ)はシャーマン・巫医の巫術により、蘇る
とされる。−シャーマンが伝承に関与して、原出雲神話・環日本海口承民話
(「死と再生」の動物寓話)が誕生する。(A.D.8C以前、A.D.1C以後)−
<アイヌ叙事文芸の源流としての巫謡、と対応するか>
5 出雲族の語り部が、その民間説話を建国の英雄神話に吸収する。
「魚族の橋」ツーク(A.D.1C以前)
8 アジアの動物寓話
1) 日本の「稲葉の素兎」と類似した経過をへて、東北アジアの環日本海諸民族およ
び東南アジアの諸民族で、その類話の動物寓話が誕生したことが考えられる。
(AT58「わにがジャッカルを運ぶ」)
比喩的にいえば、それはこれらの民族の多数のイソップがこれを語りはじめた。
イソップは、たとえていえば、笑話の吉四六とか彦市のごとき存在か。
2) 日本では、なぜ 「稲葉の素兎」は、絶後のタイプなのか。それは、記紀の「死
体化生」タイプの状況と類似している。
ただし、その登場者の「兎」は、昔話の「餅争い」(IT527A,B,C)、
「かちかち山」(IT531)、「兎の分配」(IT558)、などに継承されて
いる。
仏教思想の浸透によって、動物の畜生観が浸透し、動物寓話の登場者になりえな
くなったか。
ホームページへ
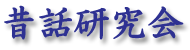 「無文字時代の動物寓話」 〜「稲葉の素兎」誕生まで〜
「無文字時代の動物寓話」 〜「稲葉の素兎」誕生まで〜